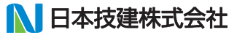排水処理設備の仕組みを解説!
排水処理設備とは?基本構成と役割を理解する

排水処理設備とは、工場や家庭などから排出される汚れた水を、河川や海などの公共用水域に放流できる水質まで浄化するための設備です。
排水処理の目的:環境基準達成と水質保全
排水処理の最も重要な目的は、水質汚濁防止法などの法令で定められた環境基準を達成し、河川や海などの水質汚染を防ぐことです。排水中に含まれる有機物、窒素、リンなどの汚濁物質は、水中の酸素を消費し、魚類などの水生生物に悪影響を与えます。また、有害物質を含む排水は、人の健康や生態系に深刻な被害をもたらす可能性があります。排水処理は、これらの汚濁物質や有害物質を除去・無害化することで、水環境の保全に貢献しています。
排水処理設備の全体フロー:一次処理から高度処理まで
排水処理設備は、大きく分けて一次処理、二次処理(生物処理)、高度処理(三次処理)、そして汚泥処理の工程で構成されます。
- 一次処理: 排水中の大きなゴミや土砂、油脂などを物理的に除去する工程です。
- 二次処理(生物処理): 微生物の働きを利用して、排水中の有機物を分解・除去する工程です。
- 高度処理(三次処理): 二次処理で除去しきれなかった微細な粒子や溶解性物質、色度、臭気などを除去する工程です。
- 汚泥処理: 排水処理の過程で発生する汚泥を減容化・安定化し、最終処分する工程です。
これらの工程を組み合わせることで、排水を環境基準を満たす水質まで浄化します。
排水の種類と特性:工場排水、生活排水、それぞれの特徴

排水は、大きく分けて工場排水と生活排水に分類されます。工場排水は、製造業などの事業活動に伴って排出される排水で、業種によって水質が大きく異なります。例えば、食品工場からは高濃度の有機物を含む排水が、金属加工工場からは重金属を含む排水が排出されます。一方、生活排水は、家庭の台所、風呂、トイレなどから排出される排水で、比較的均一な水質ですが、時間帯によって水量や水質が変動する特徴があります。排水処理設備を設計する際には、これらの排水の種類と特性を十分に考慮する必要があります。
一次処理:大きなゴミと浮遊物質を取り除く
一次処理は、排水中の比較的大きな固形物や油脂類を物理的に除去する工程です。
スクリーン処理:物理的に固形物を除去する
スクリーン処理は、排水路に設置されたスクリーンによって、排水中の大きなゴミや固形物を除去する工程です。スクリーンの種類には、粗目スクリーン、細目スクリーンなどがあり、排水の特性や除去したい固形物の大きさに応じて使い分けられます。スクリーンで捕捉された固形物は、「し渣」と呼ばれ、定期的に引き抜いて適切に処理されます。
沈砂池:土砂を沈殿させて分離
沈砂池は、排水中の土砂や砂などを沈殿させて分離する設備です。排水を緩やかに流すことで、比重の大きい土砂を沈殿させます。沈殿した土砂は、掻寄機などによって系外へ排出され、処理されます。沈砂池は、下水処理場や工場排水処理施設などで、後段の処理設備の負荷を軽減するために設置されます。
油水分離:浮上油を効率的に回収
油水分離は、排水中に含まれる油脂類を浮上させて分離・回収する工程です。油脂類は水よりも比重が軽いため、排水を静置すると水面に浮上します。油水分離装置には、自然浮上式や加圧浮上式などがあり、排水の特性や処理量に応じて使い分けられます。回収された油脂類は、再利用される場合もあります。
日本技建の課題解決事例
スクリーン

当社は独自の「IKロンメッシュ」というろ布を使用することにより、微細なSSから夾雑物まで対応が可能なスクリーンをご提供しております。また、ろ布の「詰まり」発生時に自動で復旧するタイプもあり、従来の自動洗浄タイプでも対応が難しい現場で数多く実績がございます。人がわざわざ取り除く作業もなくすことができ好評を頂いています。
>>課題解決事例はこちら
オイルスキマー
スクリーンと同じく当社独自のろ布「IKロンメッシュ」を使用したオイルスキマーは高い油分の回収率をほこります。その性能から金属加工業、ダスコン業界、段ボール製造業など数多くの現場で採用頂いています。
生物処理(二次処理)
生物処理は、微生物の働きを利用して、排水中の有機物を分解・除去する工程です。
活性汚泥法
活性汚泥法は、排水処理において最も広く用いられている生物処理技術です。ばっ気槽と呼ばれる反応槽に排水と活性汚泥(微生物群)を入れ、空気を吹き込んで好気的条件を維持します。活性汚泥中の微生物は、排水中の有機物を栄養源として摂取・分解し、増殖します。その後、沈殿槽で活性汚泥と処理水を分離します。沈殿した活性汚泥の一部はばっ気槽に戻され(返送汚泥)、残りは余剰汚泥として系外へ引き抜かれます。
接触ばっ気法
接触ばっ気法は、ばっ気槽内に接触材と呼ばれる担体を充填し、その表面に微生物を付着させて排水を処理する方法です。活性汚泥法に比べて、微生物を高濃度に維持できるため、小規模な施設でも安定した処理が可能です。また、活性汚泥の沈降性が悪化するバルキング現象の影響を受けにくいというメリットもあります。
膜分離活性汚泥法(MBR)
膜分離活性汚泥法(MBR)は、従来の活性汚泥法の沈殿槽の代わりに、精密ろ過膜(MF膜)や限外ろ過膜(UF膜)などの分離膜を用いて固液分離を行う方法です。沈殿槽が不要となるため、省スペース化が図れます。また、膜によって完全に固液分離されるため、高度な処理水質が得られます。さらに、活性汚泥を高濃度に維持できるため、有機物や窒素の除去性能も向上します。
生物処理の落とし穴
生物処理において注意すべき現象の一つが、バルキングです。バルキングとは、活性汚泥の沈降性が悪化し、沈殿槽で固液分離が困難になる現象です。糸状性細菌の異常増殖などが原因で発生します。バルキングが発生すると、処理水の水質悪化や汚泥の流出などの問題が生じます。バルキング対策としては、糸状性細菌の増殖を抑制するために、溶存酸素濃度やF/M比(有機物負荷量と活性汚泥量の比)を適切に管理することが重要です。
回分式活性汚泥法
回分式活性汚泥法は、1つの反応槽で「排水の流入」「ばっ気」「沈殿」「処理水の排出」を周期的に繰り返す方式です。反応槽が一つで済むためコンパクトな設計が可能で、流入水量の変動にも対応しやすいのが特長です。ただし、各工程の時間を適切に設定する必要があるため、高度な運転管理技術が求められます。
日本技建だから可能な二次処理装置の省スペース化

日本技建では、二次処理に追加する装置の省スペース化をご提案しています。当社の凝集ろ過装置は、凝集処理とろ過工程を一台で行えるため、凝集沈殿槽の追加設置が不要です。また、凝集沈殿槽の撤去や追加設置に伴う土木工事も不要となり、省スペース化と工事費の削減を実現します。
>>詳細はこちら

また、この凝集ろ過装置と脱水機を1台にしている「凝集ろ過脱水機」でさらなる省スペース化が可能です。
高度処理(三次処理)
高度処理は、生物処理(二次処理)で除去しきれなかった微細な粒子や溶解性物質、色度、臭気などを除去し、さらに高度な水質を得るための工程です。
凝集沈殿法
凝集沈殿法は、排水中に含まれる微細な粒子や溶解性物質を、凝集剤を用いて凝集させ、沈殿・分離する方法です。凝集剤としては、ポリ塩化アルミニウム(PAC)や硫酸バンドなどの無機凝集剤や、高分子凝集剤が用いられます。凝集剤によって形成されたフロック(凝集体)は、沈殿槽で沈降分離されます。
砂ろ過法:
砂ろ過法は、砂を充填したろ過層に排水を通水し、SS(浮遊物質)などの微細な粒子を除去する方法です。凝集沈殿処理と組み合わせて用いられることが多く、SS除去の最終ステップとして機能します。ろ過層の洗浄方法には、表面洗浄や逆流洗浄などがあります。
活性炭吸着法
活性炭吸着法は、排水を活性炭層に通水し、色度、臭気、有害物質などを吸着除去する方法です。活性炭は、非常に大きな比表面積を持つため、高い吸着能力を有します。活性炭吸着法は、排水の高度処理や排水の再利用などに用いられます。
消毒処理
消毒処理は、排水中の病原性微生物を死滅または不活化させる工程です。塩素消毒、オゾン消毒、紫外線消毒などの方法が用いられます。塩素消毒は、最も一般的な消毒方法で、次亜塩素酸ナトリウムなどの塩素剤を排水に注入します。オゾン消毒は、強力な酸化力を持つオゾンを用いて消毒する方法です。紫外線消毒は、紫外線を照射して微生物のDNAを損傷させることで消毒する方法です。
汚泥処理
排水処理の過程では、必ず汚泥が発生します。汚泥処理は、この汚泥を減容化・安定化し、最終処分するための工程です。
濃縮
濃縮は、汚泥の含水率を低下させ、容積を減少させる工程です。重力濃縮、浮上濃縮、遠心濃縮などの方法があります。重力濃縮は、汚泥を濃縮槽に静置し、重力沈降によって固液分離する方法です。浮上濃縮は、加圧浮上などの原理を利用して汚泥を浮上させ、濃縮する方法です。遠心濃縮は、遠心分離機を用いて汚泥を濃縮する方法です。
消化
消化は、汚泥中の有機物を微生物の働きによって分解し、減容化・安定化させる工程です。嫌気性消化と好気性消化があります。嫌気性消化は、酸素のない状態で嫌気性微生物によって有機物を分解する方法で、メタンガスを回収できるメリットがあります。好気性消化は、酸素を供給しながら好気性微生物によって有機物を分解する方法です。
脱水
脱水は、汚泥の含水率をさらに低下させ、容積を大幅に減少させる工程です。脱水機には、真空脱水機、フィルタープレス、ベルトプレス、遠心脱水機などがあります。脱水された汚泥は、「脱水ケーキ」と呼ばれ、焼却や埋め立てなどによって最終処分されます。
>>脱水機デモ
焼却・溶融
汚泥の最終処分方法としては、焼却、溶融、埋め立てなどがあります。焼却は、汚泥を焼却炉で燃焼させ、灰化する方法です。溶融は、汚泥を高温で溶融し、スラグ化する方法です。焼却や溶融によって、汚泥の最終処分量を大幅に削減することができます。
排水処理設備のメンテナンス

排水処理設備を長期間安定して稼働させるためには、適切なメンテナンスが不可欠です。
日常点検のポイント:機器の正常な動作確認
日常点検では、各機器が正常に動作しているか、異音や異常振動が発生していないか、などを確認します。また、流量計や水位計などの計器類の指示値が正常範囲内にあるか、薬品注入ポンプの動作状況はどうか、なども確認します。
定期メンテナンス:部品交換と性能維持
定期メンテナンスでは、一定期間ごとに機器の分解点検や部品交換を行い、設備の性能を維持します。例えば、水中ポンプのメカニカルシールの交換、ブロワーのフィルターの清掃、計器類の校正などを行います。
トラブルシューティング:異常発生時の迅速な対応
排水処理設備で異常が発生した場合には、迅速な対応が求められます。異常の原因を特定し、適切な処置を講じるためには、設備の仕組みや運転管理に関する知識と経験が必要です。トラブルシューティングの手順としては、まず、異常の発生状況を確認し、原因を推測します。次に、推測に基づいて点検を行い、原因を特定します。そして、原因を取り除き、再発防止策を検討します。
水質検査の重要性:放流水質の監視
排水処理設備の運転管理においては、放流水質の監視が非常に重要です。水質汚濁防止法などでは、放流水の水質基準が定められており、基準を遵守する必要があります。そのため、定期的に放流水の水質検査を行い、基準を満たしていることを確認する必要があります。水質検査の項目には、BOD、COD、SS、窒素、リンなどがあります。
排水処理なら日本技建にお任せください

日本技建は、排水処理の専門メーカーとして、40年にわたり、お客様の多様なニーズに応える排水処理設備を設計・製作してまいりました。前処理であるオイル回収、SS・夾雑物回収から凝集処理・生物処理まで網羅している設備を一貫してご提供しています。
また、排水処理に関するご相談や診断依頼を承っておりますのでお気軽にご連絡ください。